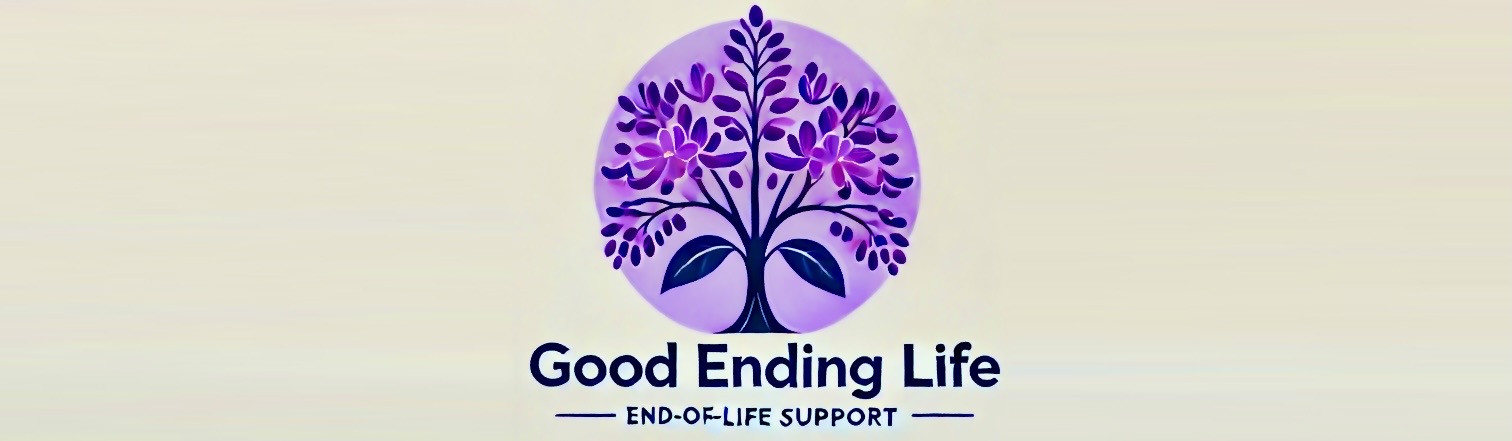はじめに
エンディングノートは,自分の最期に向けての意思を記録し,遺族やお世話になった人に意思表示するとても重要なツールです。 しかし,せっかく書いたエンディングノートも,適切に保管されていないと,いざという時に役立たない可能性があります。
最悪なケースは,厳重に保管しすぎて,そもそもエンディングノートの存在に遺族が気付かなかった…というケースです。
エンディングノートには,資産状況や暗証番号やその他プライベート関連の非常にデリケートな情報がたくさん書かれることになります。 なので,その存在を秘密にして,自身が亡くなった後に発見してもらうことを前提に準備する方もいらっしゃるでしょう。
そこで,今回はエンディングノートの適切な保管場所やその方法について解説します。
なぜエンディングノートの保管場所が重要なのか?
もしエンディングノートが発見されなければ,エンディングノートに残した記録は遺族に全く伝わりません。 また,保存方法がずさんだと汚損したり水没したりして,発見されても判読できないケースも存在します。(特に令和6年現在において,ご高齢の方ですと,非常に達筆すぎて読めないというケースもあります。)
そのため,エンディングノートは書いて終わりではなく,保管場所をしっかりと考え,家族や信頼できる人に知らせておくことが大切です。
では,具体的にどのような場所に保管するべきなのでしょうか? 以下にいくつかの保管場所や方法を挙げ,そのメリットとデメリットについて整理していきます。
方法1. 自宅の引き出し,タンスや本棚
メリット
自宅で使っている家具の引き出しやタンス,本棚は,エンディングノートの保管場所として最もポピュラーな場所です。 自宅の中に保管しますので,遺族が発見しやすく,存命中もエンディングノートを更新する際に非常にアクセスしやすいメリットがあります。
普段から使っている場所に保管しておくことで,万が一そのエンディングノートの存在を家族などに話していなかったとしても,遺品整理時に探す手間が少ないうちに発見してもらいやすいでしょう。
デメリット
万が一火事や災害が起こった場合,ノートが焼失したり,水害でダメージを受けたりする可能性があります。
また,自宅に空き巣が入った場合,貴重品と一緒に持ち去られてしまうリスクがあります。 エンディングノートは非常に盗まれやすいことにも注意が必要です。 なぜなら,エンディングノートには口座情報や暗証番号・パスワードの重要情報が記載されている可能性が高いからです。
方法2. 自宅の防火金庫
メリット
自宅に防火金庫がある場合,金庫に保管することで,火事や災害などの非常事態でもノートを保護することができます。 また,金庫には鍵や暗証番号が設定されているため,重要な情報が外部に漏れるリスクも低くなります。
遺された家族は,遺品整理時には,金庫はほぼ確実に確認しますので,ノートがほぼ確実に見つかるはずです。
デメリット
金庫のサイズによっては,エンディングノートが入りにくい場合があります。 また,金庫が重かったり,設置場所が限られていたりするため,家の中で適切な場所を見つけるのが難しいこともあります。
さらに,金庫の鍵や暗証番号を忘れてしまったり,金庫の暗証番号を家族知らない場合はノートを取り出せなくなるリスクがあります。
方法3. 信頼できる家族や友人などに預ける
メリット
信頼できる家族や友人に直接エンディングノートを預けることで,死後に遺族がすぐに・確実にエンディングノートにアクセスできます。 また,自分で保管場所を気にする必要がなくなるため,心理的な負担が軽減されます。
デメリット
プライバシーが守られないリスクがあります。 また,ノートの内容を知られたくない場合に問題となりますが,エンディングノートの内容が第三者に漏れる可能性があります。
また,預けた人が紛失してしまったり,保管場所を忘れてしまったりするリスクも考えられます。 さらに,エンディングノートを預かった人も,そのノートの保管場所に自宅や自分の金庫などを選択した場合,前述の方法1や2と同じデメリット(汚損・盗難リスクなど)が存在します。
そのため,預ける相手を慎重に選ぶ必要があります。
方法4. 弁護士や司法書士や行政書士に預ける
メリット
エンディングノートを弁護士や司法書士や行政書士に預けることで,確実な保管が期待できます。 法律の専門家に預けることで,ノートの存在が保証され,必要なときに確実に取り出してもらえるという安心感があります。
また,遺言書などと併用する際に法的な助言も併せて受けることができるため,エンディングノートと遺言書とでリンクした内容を整備できるメリットがあります。 さらに,法的な側面からアドバイスを得られることも大きな利点となります。
デメリット
基本的に,エンディングノートを預けることに対する費用が発生します。 また,依頼している弁護士や司法書士や行政書士が引退したり,急な事情で事業を終了してしまうと,ノートの所在が不明になるリスクも考えられます。
基本的には,上記のような引退や事業終了の際には,エンディングノートを返却してくれるはずです…。 が,安全のためには預けっぱなしにするのではなく,定期的に預けた士業の先生とは連絡を取るようにしておきましょう。
方法5. 銀行の貸金庫
メリット
銀行の貸金庫は,現実的にとり得る手段としてはトップクラスに安全な場所です。 金庫内は耐火性や耐震性があり,重要な書類や貴重品を保管するのに最適な環境が整っているので,汚損・盗難リスクはかなり小さくなります。
また,貸金庫に預けることで,家族や第三者が不正にアクセスすることもほぼ確実に防げます。
デメリット
いざという時に貸金庫を開けるためには,家族や信頼できる人に貸金庫の情報を知らせておく必要があります。 また,銀行が営業している時間でないと貸金庫にアクセスできないため,緊急時にすぐに取り出せない場合があります。
さらに,銀行の貸金庫は費用がかかるため,コストの面でデメリットとなる可能性があります。
方法6. デジタル保管(クラウドストレージやUSBメモリ)
メリット
最近では,エンディングノートをデジタル化して保管する方法も有力な選択肢となります。 デジタル化したエンディングノートをクラウドストレージなどに保管することで,インターネットにアクセスできる環境さえあれば,どこからでもノートの内容を確認することができます。
クラウドストレージ上のデータが消失することは非常に稀ですし,万が一の場合でもバックアップで復元できる可能性があります。
また,大手のクラウドストレージのサーバーは大規模災害に耐えられるように,サーバーが世界中に分散させてあることが多いので,災害リスクもほぼありません。
デメリット
クラウドストレージの場合,セキュリティの問題が懸念されます。 万が一,アカウントがハッキングされると,個人情報が流出してしまう可能性があります。
また,クラウドストレージではなく,デジタルエンディングノートをUSBメモリに保管する場合は,物理的な紛失のリスクがあります。
方法7. 複数の場所・方法に分散して保管する
メリット
エンディングノートを一か所に保管するのではなく,複数の場所に分散して保管することで,リスクを軽減することができます。 例えば,自宅に一部を保管し,信頼できる友人にもう一部を預けるなどです。
もしくは,方法2で物理的なノートを金庫に保管し,方法6でデジタル化したエンディングノートをクラウドストレージに保管する,というような二刀流で保管する方法が考えられます。
これにより,どこか一か所が紛失しても,他の場所でカバーできます。
デメリット
複数の場所に保管することで,管理が煩雑になるリスクがあります。 どこに何を保管したかを正確に把握し続けるためには,慎重な管理が必要です。
さらに,エンディングノートの内容を書き換えたり更新したときには特に注意が必要です。
2つ以上のエンディングノートが存在する場合,その両方をしっかりアップデートしておかないといけません。 片方だけ更新して,片方が古いと,遺族としては内容の矛盾する2つのエンディングノートが出てきたことで混乱を招く可能性があります。
保管場所を選ぶ際のポイント
エンディングノートの保管場所を選ぶ際には,以下のポイントを考慮して,自分にとってベストな方法で管理することが重要です。
- アクセスのしやすさ:緊急時にすぐに取り出せるかどうか。 見返したり,更新する可能性や頻度で検討しましょう。
- セキュリティ:盗難やプライバシーの保護が十分であるかどうか。
- 災害対策:火事や水害などのリスクに対応できるかどうか。
- 家族や信頼できる人への情報共有:保管場所を知らせておくことで,確実に見つけてもらえるかどうか。
さいごに
エンディングノートをしっかりと書くこと,そしてそのエンディングノートの内容はもちろんとっても重要です。 しかし,その保管場所も同じくらいとっても大切です。
せっかく時間(とお金)をかけて準備・用意したエンディングノートです。 それが発見されず埋もれてしまっては,元も子もありません。
自身の身の回りの環境や,家族とのコミュニケーションから,最適な保管方法でノートを大切に保管してくださいね。